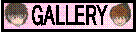「桜庭」
そう声をかけられて振り向くと、いつにもまして真剣な表情をした進がいた。
長年の付き合いで、どうやらかなり切羽詰まった頼みごとがあるらしい、と察した桜庭は、胸に萌しかけた嫌な予感をごまかしつつ、
「どうしたの? 」
と笑顔で訊ねた。
「少し話しがある」
「うん、だからなに? 」
「…ここでは言えない」
進が珍しく――というか、初めて――周囲を気にする素振りを見せたので、それでは、と練習後、誰もいなくなったミーティングルームで、じっくり腰を据えて話しとやらを聞くことにしたのだった。
しかし、蛍光灯と椅子と机と桜庭しかいない状況になっても、進は黙ったまま、なかなか口を開こうとしない。
「えーと、あのさ、そろそろ話してくれないかなあ。俺、腹減ってきちゃったし…」
「…すまん」
「そんなに話しにくいことなの? 」
桜庭が踏み込むと、進は眉を顰めて、いや、と歯切れの悪い返事をした。
「また自動販売機壊したとか? それとも、誰かの携帯逆パカした? 」
「…ちがう」
「えー、じゃあなに? 好きな子でも出来たの? 」
桜庭としては、あくまでも冗談のつもりのつっこみだった。
しかし、途端に腹でも痛くなったような顔つきになり、うんともすんとも言わなくなった進を見て、まさかの図星であることを確信したのであった。
「ほ、ほんとに? 好きな子出来たの? ね、ちょっと、黙ってたらわかんないだろ? 」
桜庭の剣幕に押されて、進はついにはっきりと頷いた。
いったん話が見えてしまえば、後は聞き出すのも簡単だった。
進はもう数ヶ月ほど前から、ある後輩に密かに好意を寄せていた。
始めは自分の胸の内にだけおさめておこうと思っていたのだが、やはり想いの丈は募り募って、相手に気持ちを伝えたいと願うところにまで至ったというのである。
桜庭は涙を流さんばかりに感動しながら、進の純情なうちあけ話に聞き入っていた。
あの、規則正しい生活と苦行じみたトレーニングにしか眼を向けなかった進が、とうとう異性に興味を持ったのだ。
他の友人から「進て人間ぽくないよな」などと無遠慮なことを言われ続けてきた桜庭にとっては、まさに快哉を叫びつつ餅でも配りまわりたい気持ちだったのである。
「わかった! 俺、進とその子がうまくいくように、全力で応援するから! 」
桜庭は、まかせておけという勢いで、進の肩を力強く叩いたのだった。
「で、1番肝心なトコなんだけど…お相手は誰なの? 」
もはや好奇心を抑える必要はないと、桜庭は進の顔をのぞきこむようにして訊ねた。
進の方も、ここまできたらと腹を決めたらしい。
顔色を変えることもなく、常のごとく簡潔に、
「小早川セナだ」
と返したのだった。
桜庭は、もちろん、絶句した。
小早川セナ、という名前は桜庭も知っていた。
たしかに、自分たちよりも学年は1つ下の後輩にあたる。
進がなにかと気にかけている存在であることも把握している。
しかし。
しかし、だ。
「進…。俺の思い違いでなければ、セナくんは、男…」
「手を貸してくれるのだな。ありがとう、桜庭」
進はそう言うと、顔面蒼白で石化している桜庭を残して、帰り支度をするためにいそいそと部屋を出て行った。
そういえば、進からありがとうって言われたの初めてだな――半ば以上魂が抜けた頭で、桜庭はぼんやりとそんなことを考えていたのだった。
*
その後一晩眠れぬ夜を過ごした桜庭だったが、1度意気込んで応援すると言った以上、進の告白に協力しないわけにもいかなかった。
桜庭は、最初に話を聞いたミーティングルームを事実上の作戦会議室にして、昼休みごとに昼食を食べながら、進と相談をくりかえした。
「やっぱり、直接言うってのが1番いいと思うんだよね」
桜庭が卵焼きを頬張りながらそう言うと、進は渋い顔をしたまま箸を持つ手元に眼を落とした。
その様子を横目に見ながら、桜庭は肩を竦めて溜息をついた。
普段の物怖じしない態度からは想像がつかないが、蓋を開けてみれば、進はかなりの奥手なのだった。
いつも通り、猪のごとくセナに突進していくのかと思いきや、それはあくまでも勝負の時の話で、色恋沙汰はその限りではないというのだ。
めんどくさいなあ、と心中で呟きつつ、桜庭は焼のりで巻いたおにぎりにかぶりついた。
しばらくもしゃもしゃと口を動かしてのみこんだ後、おもむろにまた進の方を見て、
「じゃあ、手紙書こう」
と提案したのだった。
IT全盛のこのご時世に、メールではなく手紙というのは古風もいいところだが、あいにく、進自体が古風を通り越して化石のような男で、携帯電話もパソコンもからっきしなのだから仕方がない。
「むしろ、今だからこそ、手書きの手紙って、ぐっとくるかもよ」
女の子の場合はだけど、の一言は胸にしまい、桜庭は更に水を向けた。
進は、なるほど、と感心したようにつぶやいた。
どうやら、お気に召したようである。
「そうと決まれば、便箋買いに行こうよ」
「ああ、たしか購買部に売っていたような気がするが…」
進の何気ない一言に、桜庭は眼を剥いて、
「ばっっかじゃないの!? 」
と叫んだ。
桜庭の突然の怒りに、進は面食らって動きを止めた。
「あのね、進。今からお前は、好きな人に告白するための手紙を書くの。つまりそれは、セナくんに、お前のことを気に入ってもらうために書く手紙なんだよ!そんな大事な手紙に、学校の購買に売ってるようなテキトーな便箋使っちゃだめだろ!? ちゃんとした文房具屋に行って、かっこいいの選ぶんだよ! 」
「……そういうものなのか」
「そういうもの! 今日の練習終わったら、すぐ買いに行くからな! そのつもりでいろよ! 」
いつになく強い桜庭の語気に、進は反論の余地なく頷いたのだった。
ちゃんとした文房具屋、といっても、進にそんな店のあては全くなかった。
だが桜庭は、お前の情報なんて最初からアテにしていない、と言わんばかりの態度で、校門を出るとさっさと進の前を歩きだしたのだった。
そうして2人は、幾度か電車を乗り換え、華やかな都心の駅に降り立った。
帰宅途中のサラリーマンや、これから遊びに行くらしい男女の姿で賑やかにごった返している構内を過ぎて外へ出る。
更に密度を増した人混みをするするとすり抜け、桜庭はどんどん前進して行った。
都市の喧噪に馴れていない進は、桜庭の姿を見失わずにいるだけで精一杯で、今自分がどこを歩いているかすら、皆目見当がつかなかった。
いくつかの角を折れて大通りから離れ、やっと人の数も減って身動きもしやすくなったと思ったとき、桜庭の足がぴたりと止まった。
「ここ。便箋と封筒の専門店」
そう簡単に説明して、桜庭は自動ドアをくぐった。
フロア自体はさして広くないが、とにかく、棚という棚に様々な便箋や封筒、グリーティングカードなどが陳列されている。
形も色も大きさも、実に多彩だ。
「すみません、ちょっと便箋を買いたいんですけど、一緒に選んでいただけませんか? 」
進が商品の量に圧倒されている間に、桜庭は、自分たちのすぐ近くで在庫整理をしていた若い女性店員に声をかけた。
店員は、わかりました、とにこやかに頷いて、レターセットのコーナーに案内してくれた。
「どのようなお手紙にお使いですか? 」
「ラブレターです」
進がなんと答えたものかと逡巡する前に、桜庭がズバリと返した。
相手は、今時珍しいと思ったのか、眼を丸くして、ラブレター、とおうむ返しに言った。
「はい。でも、俺が書くんじゃないんです。コイツの方なんです」
桜庭の言葉に、進はぎょっとして彼の横顔をまじまじと見た。
すると、桜庭も進の方に振り向いて、
「な? 」
と同意を求めてきたので、進は思わず首を縦に振ったのだった。
そんな2人のやりとりを微笑ましげに見ていた店員は、改めて進の方に向き直ると、
「どんなイメージでお探しですか? 」
と訊ねてきたのだった。
今度は、桜庭も助け舟を出さなかった。
進は、イメージ、と口の中で繰り返したまま、困り果てて押し黙るしかなかった。
途方に暮れた進を見て、店員は苦笑すると、
「お相手はどんな印象の方なんですか? 」
と別の方向から質問をしなおした。
進の頭の中に咄嗟に浮かんだのは、自分を見上げてくる凛としたセナの表情だった。
「…芯の強い眼をしています」
かろうじてそう答えると、店員は、なるほど、と言って、並べられたレターセット類をしばし思案顔で眺めていた。
「――こちらはいかがですか? 」
差し出されたのは、薄くグリーンがかった用紙の右上と左下にレースの文様が入った便箋と、同色の封筒が入ったものだった。
罫線もほどよいブラウンで、シンプルだが地味ではない。
「あとは、こちらもすてきですよ」
そう言われて見せられたのは、ろう引き紙を使った封筒と、やや茶色みを帯びた紙に同系色の縁取り模様がついた便箋のセットだった。
そうして候補を出してもらったものの、どちらがよりよいのか、はたまたこれらではないものの方がよいのか、進にはとんと判断がつかなかった。
仕方なく、助けを求めるつもりで桜庭の方を見た。
さっきから口を挟まずにレターセットの棚を冷やかしていた桜庭は、進の視線に気付くと、
「進の好きなのを選べばいいんだよ」
とだけ言った。
好きな、とは、つまり気に入ったということだろう。
そう考えた進は、最初に出された方を手に取った。
会計を済ませて店の外に出た時、桜庭は、
「どうしてそっちにしたの? 」
と訊いてみた。
進は少し考えてから、
「泥門の制服の色に似ていたからだ」
と答えたのだった。
*
手紙を書くにあたって、桜庭は進にいくつかの注意を与えた。
長さの上限は便箋1枚半。
下書きは適当な紙に行い、文面が確定するまでは便箋を使わないこと。
そして、誤字脱字にはくれぐれも気を付けること。
「お前に限ってとは思うけど、こういう手紙で字を間違うと、マジで恥ずかしいからさ」
桜庭は別れ際にそう付け加えて、頑張れよ、と笑って手を振った。
友人の励ましに応えるべく、その週の土日の空き時間全てを費やして、進はセナへの手紙を見事に書き上げた。
月曜日にその報告を受けた桜庭は、やったやったともろ手を上げて喜んだ後、
「で、どうやって渡そうか」
と次なる課題を進につきつけた。
そして、わざと大袈裟に深刻な表情を作って、
「まー、こればっかりは、直接手渡すしかないな」
と宣告したのであった。
動揺した進が、反射的にあとずさりかけると、
「最低限の誠意だ! 」
とすかさず一喝した。
「1人で行けとは言わないよ。俺もうしろからこっそり応援しててやるからさ」
気が進まぬ相手の首根っこを半ば無理やりひっつかむような形で、早速その日の放課後、桜庭は進と連れ立って黒美嵯川に出かけて行ったのだった。
告白の手紙を渡すのに、いつものパーカースタイルというのはいかがなものか、という桜庭の意見で、進はあえて制服姿のまま、セナが姿を現すのを待っていた。
セナのランニングコースと、彼が王城と泥門の中継地点である黒美嵯川に現れる時間帯は、進の弛まぬ検証によってほぼ確定されていた。
それを聞いた桜庭は、友人のストーカーとしての素質の高さに、少なからず震撼した。
が、今は深く考えずに、大抵こちらから走ってくるといって進が示した方向に眼を凝らし、目的の人物を見失わぬよう細心の注意を払っていた。
「――来た」
「え、どこどこ? 」
進のわきから身を乗り出して見てみると、なるほど、特徴的なセナの髪型がこちらへ向かって近づいてくるのがわかる。
「ほら、行ってきな! 」
そう促したが、進は桜庭の顔とセナのやってくる方向を交互に見たまま、足を前に出そうとしない。
「いや、お前、ここまで来てなにためらってんの!? 」
さすがに腹が立って、桜庭は素っ頓狂な声を上げた。
そうこうしているうちに、セナの姿はどんどん大きくなり、ほどなく2人の前にたどりついてしまったのだった。
「あれ? 進さんと、桜庭さん? こんにちは」
足踏みをしたままの状態で、セナはペコリと頭を下げた。
「制服姿でお会いするのって、珍しいですね。今日は、王城は練習お休みなんですか? 」
セナの質問に、進と桜庭は顔を見合わせて、そうだともちがうともつかない曖昧な返事をした。
しかし、セナはさして不審に思うこともなかったようで、そのまましばらく天気の話などをしてから、
「それじゃあ、失礼します」
と元気よく挨拶をして、足音も軽く立ち去って行った。
また遠ざかっていくセナの後ろ姿を見て焦った桜庭は、
「おい! 行けってば! 」
と進の背中を思い切り叩いた。
だが、進はこの期に及んでまだまごまごしている。
当のセナは、ますます離れて行ってしまう。
「さっさと行けーっ!! 」
とうとう堪忍袋の緒が切れた桜庭は、進の尻を力任せに蹴飛ばしたのだった。
油断していたところを、背後から思い切りつきとばされた格好になった進は、転びそうになるのをなんとか堪えて態勢を立て直し、セナの方へ一目散に駆けて行った。
制服の走り辛さといったらなかったが、それでも持ち前の脚力でほどなくセナに追いついた。
「ま、待ってくれ、小早川…! 」
「…え、えぇっ? し、進さん、どうしたんですか? 」
さすがに足を止めたセナは、妙に息を切らしている進を前にして、眼を白黒させた。
「ぼくになにかご用ですか? 」
こうなったら後には退けない。
進は、上着のポケットから例の手紙を出すと、
「受け取ってくれ」
と言って、セナの鼻先に突き出した。
「て、手紙…ですか? 」
思いもかけないものを渡され、セナは更に驚いた。
「これ、誰かに渡せばいいんですか? 」
まさか自分宛てだとは思わずにそう訊ねると、進は、ちがう、と首を横に振った。
「お前に読んでもらいたい」
「え、ぼくですか? えーっと、わかりました…」
事態はまったくのみこめないが、進の必死の形相に、セナはとりあえず頷いた。
「たしかに渡したぞ」
不自然に時代がかった台詞を残して、進はあっという間に元来た方へ駆け戻って行った。
セナは、その電光石火の速さに、進さんはやっぱり凄いな、と感心しながらも、
「そういえば、返事って、どうすればいいんだろう…」
と首を傾げたのであった。

*
「おーい、セナぁ、いるかー!? 」
そう叫びながら、モン太は部室のドアを勢いよく開いた。
返事が無かったので、てっきりまだランニングから帰っていないのかと思いきや、テーブルの前に置かれた椅子に腰かけて、神妙な顔をしているセナを見つけたのだった。
「なんだ、いるんだったら返事しろって! 」
「うん…」
どこか上の空なセナの返事に、モン太はどうかしたのかと心配になった。
「どうしたんだよ、元気ねえじゃん。どっか具合悪いのか? 」
「ううん、そういうわけじゃないよ」
「でも、なんか変だぜ? 」
モン太は気遣わしげに言うと、自分も椅子を引っ張って来てセナの隣に座った。
ふと、テーブルの上を見ると、開いた封筒となにか書かれた便箋が置いてあった。
「あれ、なんだこれ」
不思議に思って手に取ろうとすると、待って! とセナが慌てて制した。
「あ、これセナのか」
「うん、さっき貰ったんだ」
セナがそう答えた途端、モン太の瞳が鋭く光った。
「ぬわにぃ~? さっき貰っただと~? もしや…カワイイ女の子からか!? 」
「いやいやいや、ちがうよ! 進さんから貰ったんだよ!! 」
セナが全力で否定すると、モン太は、あっそう、と言って、元のあっけらかんとした顔つきに戻った。
「ん、でも待てよ? お前今、進さん、て言ったか? 」
「うん…」
「進さんが、なんでわざわざ手紙なんか渡してくんだよ」
「わかんない」
セナの答えに、モン太は首をひねった。
「わかんないって…。手紙はもう読んだんだろ? 」
「一応、読んだけど…」
「じゃ、用件は分かるだろ? 」
「それが、難しい言葉が多くて、内容がよくつかめないっていうか…」
「そんなことあるかよ、貸してみろって! 」
モン太は素早く便箋を取り上げると、嬉々として文面を追いだした。
が、すぐに眉間に皺が寄り、うー、だの、あー、だのといった唸り声が口から洩れ始めたのだった。
「ね、難しいでしょ? 」
「たしかに…こりゃあ、難しいな…」
モン太はセナに手紙を返すと、素直に同意した。
端整な文字で書かれたその手紙は、画数の多い漢字と、複雑な言い回しに満ちていた。
なにを言わんとしているかを汲み取る以前に、まずは漢和辞典を引っ張り出して読み方から調べなければならない、といった箇所も多かった。
「困ったなあ…。返事、どうしよう」
セナとモン太が、額をつき合わせて悩んでいると、部室のドアが開く気配がした。
「テメーら、なにサボッてやがる!!」
「ひええっ、ヒル魔さん…! 」
こめかみに青筋を立て、マシンガンを片手に仁王立ちしているヒル魔を見て、2人は震えあがった。
「ランニングが終わったんなら、さっさと着替えてグラウンドに出てきやがれ! 」
「は、はい、すみません…」
セナが小さくなって謝ると、モン太がその前に立ち塞がって、
「違うんスよ、ヒル魔さん! 俺ら、サボッてたわけじゃないんです! 」
と反論した。
「実はセナが、進先輩から手紙もらったんスけど、内容がすげえ難しくて…」
「あん? あの糞バケモンが手紙だぁ? 」
ぞっとしねえな、とヒル魔は吐き捨てるように言った。
「んで、俺が思うに、これは進先輩からセナへの果たし状じゃないかと」
「見せろ」
モン太の言葉をスルーして、ヒル魔はうしろに隠れていたセナの手から、躊躇なく便箋をひったくった。
しばらく無言で文章を目で追っていたが、すぐにこの世のものとは思えぬほど邪悪な笑みを浮かべて、セナの顔を見たのだった。
「おい、糞チビ」
「は、はいぃ…」
なにを言われるのかとびくびくしながら、セナは蚊の鳴くような声で返事をした。
ヒル魔はどこからともなくデジカメを取り出して、便箋を撮影しながら、心の底から愉快そうにこう言った。
「進が、テメーとヤリてえってよ! 」
一瞬の沈黙の後、セナとモン太は地球の裏側にまで届くのではないかと思うほどの絶叫を迸らせたのだった。
「そ、そんな、まさか、進さんが、そんなまさか」
「そうっスよ、ヒル魔さんなんてこと言うんスか! 」
耳まで真っ赤になってパニックに陥ったセナとモン太を尻目に、ヒル魔が悪魔のような高笑いをしていると、
「ちょっと! 今の大声なに!? 」
とマネージャーのまもりが飛び込んできた。
まもりは、お構いなしにゲラゲラ笑っているヒル魔と、ゆでダコのように赤くなって口をパクパクさせているセナとモン太を見て、一体なにごとかと眼を見張った。
と、目敏い彼女は、いつの間にかヒル魔の手から床に落ちていた件の便箋を見咎めて、すぐに拾い上げた。
なんの書類? とつぶやきながら、なにげなく紙面に眼を落とした彼女は、あら、と小さく叫んで、さっと頬を赤らめた。
「これ、ラブレターじゃない…。しかもセナ宛て…。すごく情熱的な文章…なんだか私まで照れ臭くなっちゃうわね、これ、一体誰からの……え…進清十郎、って…ちょっと、セナ! この手紙はどういうことなの!? 」
差し出し人の名前を見た瞬間に母親スイッチの入ったまもりの怒号が響き渡り、室内の混迷はますます深まっていったのであった。
その後も幾多の紆余曲折があったものの、進はセナと想いを通わせることになんとか成功した。
しかし、その代償として、ヒル魔の例の手帳には、世にも珍しい「王城ホワイトナイツのエース最大の弱み」が永久に刻印されることとなったのだった――
「いやあ、進くんは本当に名文家ですなあ!」
「…!! ヒル魔ッ…! 」
めでたし、めでたし!
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――